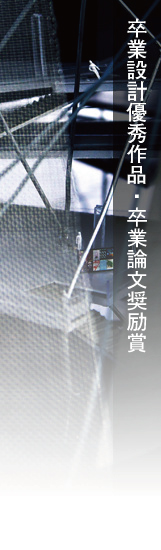
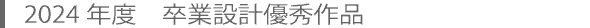
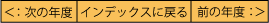
優れた構想力と高い表現力を示す創造性ある卒業設計作品の制作者に対して、その努力を称えることを目的とする。
本年度は 2 月 21日 (金)に選考が行われた。第一次審査として、常勤の教員が展示会(2/18〜2/21)にて公開された設計図面に基づき審査し投票した。午後の発表会に引き続き、第二次審査を常勤の教員および計画系非常勤講師・招へい教員 28名により行った。なお、第二次審査では、講評対象作品の選定と作品ごとの意見交換までは学生に公開している。第二次審査の経過を以下に記す。
初めに、午前中に実施された第一次審査の投票で 2 票以上の得票を得た作品と得票数を公表した。例年 3 票以上を得た作品を講評対象としているが、今年度については、1票を得票している5つの作品も講評に値するレベルにあることを確認し、1票以上を得た 17作品について講評文を作成することとした。
第二次審査に移り、各作品について評価するべき点、不十分な点を整理した。学生の退出後、受賞候補作品を絞るための投票を挙手にて行った結果、6作品を受賞候補とした。
続いて、これら 6作品を対象に作品ごとの特徴について意見交換を行い、5 作品を最優秀賞・優秀賞の対象とした。さらに、当該の 5作品について、最優秀賞を選ぶための意見交換を行ったところ、最優秀賞に相応しい作品がないとの意見が複数名より出されたことから、さらに議論を継続した。最終的に、最優秀賞を選定するか否かについて挙手による投票を行い、最優秀賞を選定しないという投票が過半数をこえたため、最優秀賞作品はなしとし、当該の5作品を優秀賞として以下のように決定した。
【選考方法】
選考は第一次審査と第二次審査の二段階で行う。一次審査により講評対象作品を、二次審査により最優秀賞・優秀賞作品の選定を行う。選考の対象は卒業研究提出日に提出された設計図面である。ただし、一次審査においては模型および展示講評会における質疑応答を評価の参考とし、二次審査においては一次審査の評価項目に加え、卒業設計発表会におけるプレゼンテーションを評価の参考とする。
【一次審査】
建築工学部門所属の全教員が、各自最大5作品を選び、それぞれに1票を投じ、得票数の多い作品から十数点を講評対象作品とする。
【二次審査】
建築工学部門所属の全教員および計画系非常勤講師・招聘教員が、一次審査の結果と公開審査を経て投票を行ない、最優秀賞および優秀賞若干名を選定する。
【卒業設計最優秀賞】
該当なし
【卒業設計優秀賞】(名簿順)
・木内 春希:Architectural Harmonics ―和声感覚による拡張空間―
・木多 翔駿:水、脈々と紡ぐ
・田淵 優希:川が都市に還るとき
・中尾 雅:Abese地区再編計画 −私が感じた美しい暮らし−
・中西 智礼:灰と白の往来に −廃スキー場へのRe-entry構想−
【全体講評】
卒業設計はそのテーマや内容を学生が自由に決めることができるが、そこで提案したものがどのような意味(価値)を持つのか、それが独り善がりの主張ではなく、より多くの人の共感を得られるかは問われることになる。卒業設計のテーマは多様であり、一律に評価するべきでないにしても、それが提案するに値するかどうかについては意識的である必要があろう。
今年の卒業設計でも審査員に高く評価された力作が多数みられたものの、ひときわ心を奪われる作品と言うにはもう少しとして最優秀作は選ばれなかった。まずテーマとして最も多かったのは主に作者の実家に関わる問題やその出身地の抱える地域的課題を扱ったものであった。それはある意味で個人の領域にある対象である以上、そこでの問題提起を否定されることはないが、その提案が如何に人の心に響くかで評価が変わってくる。
今年の作品の中で廃スキー場を扱った提案はこれまでのリゾート開発に対する懸念を背景としながらも、壮大な自然の中に加えられた建築的操作が洗練されたアートワークとして秀逸であった。一方、岡山の田園地帯を扱った作品は作者が発見した用水のサイフォン原理を解き明かす旅であり、作者のセンスオブワンダーを見つける旅でもあった。また都市と自然の浸食として説明された玉川上水の作品は、役目を終えた上水を再び街に水を引き込むことで地域を蘇らせる取り組みとして理解すれば本来の価値が見えてくる。また今年は家族の自宅の将来計画を提案する作品が多数みられたが、その構想はやや冗長で、それによってもたらされる建築的意味に言及するものは少なかった。ただその中で異彩だったのはルソーの教育論を元に自己を内省的に見つめ直すことで自宅の改造を試みた作品で幼年期の教育環境のあり方を問う問題作として迫力があった。またそれ以外で特筆すべきものとして建築造形に音楽理論で切り込んだ作品があった。もともと形を持たない音楽の感覚的な身体性を緻密な操作によって建築化を試みたもので、建築が組み立てられていくプロセスは華麗であった。またアフリカの非正規市街地のコミュニティ改造を扱った作品は緻密な現地調査をもとにしており、我々が感じる衛生面での懸念を越えて生活の「美しさ」を見出した作者が、現地のコミュニティの状況を読み取って、現地の材料や工法を用いてセルフビルドも可能な将来計画を立案した作品として高く評価したい。
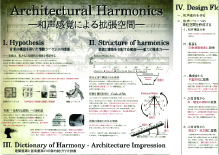 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
【講評】
この作品は音楽理論をもとに建築造形を試みた習作である。これまでも列柱のリズムや窓の配置などで音楽との類似性は議論されてきたが、ここではもともと形を持たない音楽によって想起される感覚的な身体性を緻密な操作によって建築化したもので、それが組み立てられていくプロセスは華麗で、その造形は繊細かつ魅力的である。ここでその造形操作の論理的正当性や妥当性の議論はあるかもしれないが、これはあくまで造形のための思考的試みとして理解すべきであろう。かつてバウハウスの教師をしていたカンディンスキーは抽象絵画の父といわれるが、音楽という目に見えないものを、色と形で表現したその作品が、彼の抽象表現のはじまりとされ、その絵画は音楽から受けた印象を平面に落とし込み視覚的に表現しようとする試みだったと言われている。この作品は同様に音楽という目に見えないものを、建築として造形化しようという挑戦と考えることができる。建築は視覚表現だけでなく空間体験を伴い、そこに実用としての機能が存在することで絵画とは異なっている。しかしカンディンスキーがシェーンベルグの革新的な音楽技法を絵画に応用したように、ここでもそれによって建築の新たな様式が生まれることを期待したい。
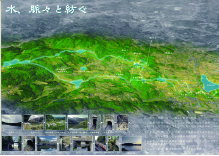 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
【講評】
100年ほど前に瀬戸内式気候で水不足に解消する目的で灌漑システムをつくり,棚田と池・用水による美しい風景を作り上げた.時が流れて人口が減少した現在も使われている灌漑システムを後世にも伝えていくために,目に見えているようで見えていない用水にささやかであるが小さな建築を設計した.それは新しい風景をつくるとともに灌漑システムを維持管理する生活者に寄り添う形で用水を守る役割を果たしている点を評価する.それであるからこそ,地域の風土に根ざしたアプローチも必要であるが,単純な形態の操作だけで建築を作り上げている点が惜しまれる.また未来へ歴史を紡ぐのであれば灌漑システム全体を捉える視点も持つべきであっただろう.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
【講評】
玉川上水はかつて、江戸の人口増加に伴う飲料水確保のために多摩川から水を引いた重要な水インフラであった。現在の玉川上水は、人為的管理から離れた部分で、自然環境が再生している。作者は逆説的に、人間の管理から外れた空間に自然の再生力が働いている事実に着目し、「自然が都市を侵食していく」ことで、自然と都市の新たな共生関係を模索している。「自然を侵食させる建築(呼び水)」を玉川上水の約30kmという線形の水空間に対して戦略的に配置するという構想は、自然の力を都市計画に積極的に取り込む革新的な提案として秀逸である。また、都市開発における人間中心主義を再考し、人間を含む生態系全体を視野に入れた都市計画の必要性を示唆している点は、現代の環境問題や持続可能性の課題に対する重要な問いかけとなっている。一方で、作者が設定した呼び水が時代とともに、どのように都市に滲み出(侵食)し、豊かな生態系の広がりを作りだすかについての説明が不足していた点はさらなる研鑽を期待したい。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
【講評】
本作品は、アフリカ・ガーナの非正規市街地であるAbese地区に対する再編計画の提案である。
作者は、現地調査より、既存の地域住民の生活を美しいと捉え、住民の行動や振る舞いが生まれる社会・空間構造を読み取り、それらを継承する再編計画を試みている。そこには、既存の住環境問題を改善するためのインフラ施設を軸としながらも、地域住民の行動や振る舞いを継承するための様々な空間がヒューマンスケールから提案されている。さらに、地域の材料や工法を用いて、地域住民が住環境を段階的に増築していくプロセスを提案し、地域の文脈が途切れず継承していく再編のあり方を追究している。作者は、既存の地域に宿っている住民の生活や記憶を継承するための仕組みを丁寧に提案する。しかしその一方で、継承の仕組みは、既存の空間構成を引用することに留まっており、地域住民の生活がなぜ美しいか、その本質を作者の視点で翻訳する過程が欠けている。地域に新たな変化をもたらしながら地域文脈を継承するための作者独自の提案について更なる検討が必要である。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
【講評】
御岳のスキー場跡地に開発の履歴と開発によって得られた恩恵を訪れた人が考える人と自然の関係を問いかける作品である.ありのままの自然と開発の跡が顕著に現れるスキー場跡地4箇所に固有の履歴と恩恵を体験できる建築空間を設計している.敷地を丁寧に読み取り,慎重な形態操作を行うことで美しい建築を作り上げ,それによって中立的な視点から人と自然の関係の問いかけが実現できている.またそこで体験できる空間を図面に表現する点も優れている.しかしながらそれぞれの建築の関係が読み取れない点,ひいてはスキー場跡地全体で得られる体験がどのようなものであるのかがわからない点が惜しまれる.
